幌加内町では「広報ほろかない」という広報誌を毎月町民に向けて発行しています。
http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/町からのいろんな情報が載っているんですが、「町立病院から」というコーナーでは毎月、いろんな医療情報や町立病院の介護部門の様子などをお伝えしています。
で、今日は今月号の原稿をご紹介します。
「がん」をワクチンで防げるって本当?子宮頸がんとは子宮頸(けい)がんとは子宮の入り口(頸部)にできるがんで、日本では年間約8000人がこのがんになり、約2400人が亡くなっています。この子宮頸がんは発がん性「ヒトパピローマウイルス(HPV)」というウイルスに何回も感染することが原因ということがわかっています。
女性の8割は一生のうちで1回以上感染すると言われ、若い女性ほどこの発がん性HPVの感染率が高く、日本人の15〜19歳の約3割が感染していたというデータもあります。もちろん、この発がん性HPVに感染しても必ずがんを発症するわけではなく、感染してもほとんどは自然に治りますが、繰り返し感染する可能性があり、HPV感染者の1%未満に十数年かけてがんが発症すると考えられています。
発がん性HPVにはいくつかの種類があり、このうちHPV16型と18型が子宮頸がんの6割(20〜30代では8割)を占めています。性交開始の若年化により20~30代の子宮頸がんが日本では急増しています。
子宮頸がんのワクチン
このHPV感染を予防する(=子宮頸がんを予防する)ワクチンは世界ではすでに100カ国以上で使用されていましたが、ついに昨年12月より日本でも発売が開始され、町立病院でも接種できます。
このワクチンはHPV16型と18型に対するワクチンでこれらの型が原因の子宮頸がんを90〜100%予防します。
現時点ではすくなくとも6年は効果が持続することが確認されおり、推計では少なくとも20年間は効果が持続するとされています。
ワクチンの対象は10歳以上の女性です。最も効果的なのは性交経験前なので、小児科学会と産婦人科学会は11〜14歳でのワクチン接種を最も勧めています。すでにHPVに感染歴があるひとにも再感染を予防する効果もあるので、15〜45歳が次に勧められています。
ワクチンの副反応としては接種時の痛みがありますが、その他の重い副反応は他のワクチンと同様に低く、安全性も確認されているワクチンです。
前述の学会も公費接種を提言していますが、残念ながら現時点では「任意」接種のため全額自己負担となります(幌加内町では新年度より中学生女子に対して全額助成を計画中)。
接種は計3回必要で、3回で4万円ほどかかります。お金はかかりますが子宮頸がんの6~7割を確実に予防でき、少なくとも20年は効果が持続すると考えると年間2千円ほどの負担という計算になります。
子宮がん検診も大切です
子宮頸がんワクチンは、全ての発がん性HPV感染を予防できるわけではないので、接種後も定期的な子宮がん検診は受けなければなりません。
欧米先進国での子宮がん検診の受診率は7〜8割と高いのですが、日本では2〜3割で特に若い世代では1~2割に満たないようです(幌加内町での昨年度の子宮がん検診の受診率は45%)。
子宮頸がんは進行すると子宮を摘出しなければならないこともあり、早期発見のためには20代からの定期的な検診受診が大切です。
ワクチンと定期的な検診を受けることで子宮頸がんの9割以上は予防できると言われています。
ご不明な点は、町立病院までお問い合わせください。
・・・と、こんな感じで毎月原稿を書いています。
わかりやすく書いたつもりなんですが、いかがでしょうか?
町民の方への健康情報、医療情報の発信も「地域医療」の大事な仕事のひとつと考えちょります!
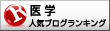
↑広報ほろかないと定期購読したいあなたはクリック。そうでもないあなたもクリック。


